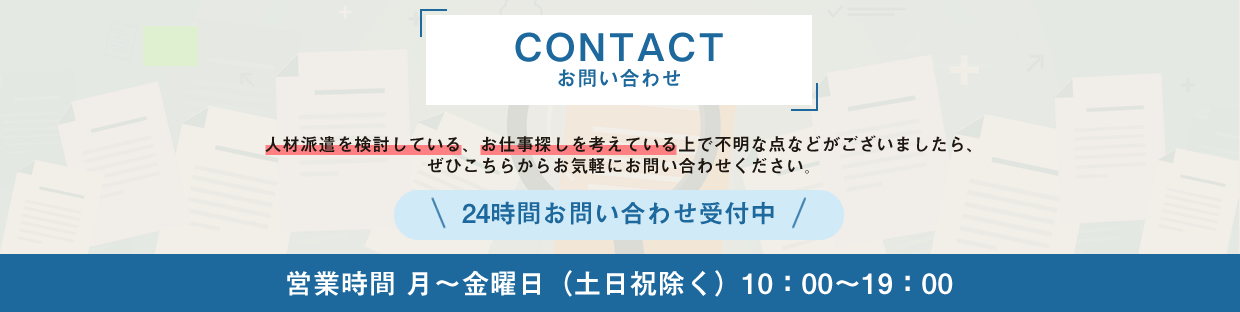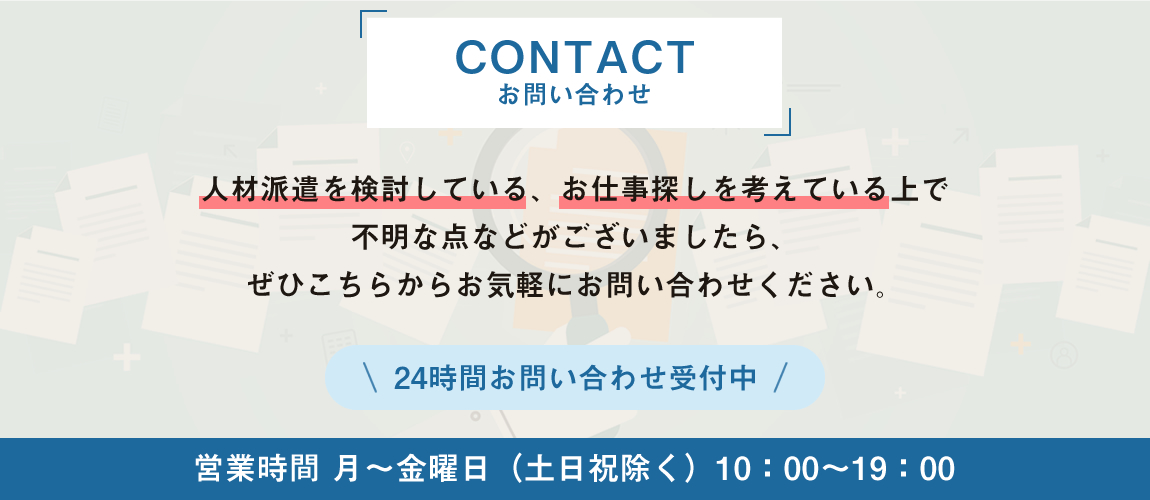日本のタクシー業界は今、大きな変化の局面を迎えています。深刻な人手不足と高齢化に直面するなか、注目されているのが「特定技能」制度を活用した外国人ドライバーの採用です。
今回の記事では、なかでもベトナム人ドライバーに注目し、都市部と地方で進む採用の動きや、登録支援機関による支援体制、今後の可能性について掘り下げます。
国土交通省の発表によれば、タクシー運転者数は2004年の約34万人から、2022年には21万人弱まで激減しています。コロナ禍の影響も相まって、再就職しないドライバーが多数発生し、地方では「移動難民」も生まれ始めています。
こうした背景を受けて、2024年3月、国はタクシー業務を「特定技能1号」の対象職種に追加。これにより、日本語能力や二種免許取得を条件に、外国人材が合法的にタクシードライバーとして働ける道が拓かれました。
外国人材の受け入れには、「登録支援機関」の存在が欠かせません。
言語サポートや住宅手配、生活支援など、外国人ドライバーがスムーズに業務に就けるよう、支援内容の充実とマッチング体制の整備が進んでいます。
さらに、企業側は「紹介」を通じて、よりニーズに合う人材を獲得しやすくなっており、特定技能外国人に特化した請負型の支援サービスも登場。とくに大阪など都市圏ではこの仕組みが拡充されつつあります。
特定技能外国人を採用する過程で登録支援機関を活用するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
注目すべきは、こうした取り組みが地方にも波及しつつあることです。
たとえば、徳島県では広沢自動車学校グループがベトナム南部ドンタップ省と連携し、特定技能外国人としてのタクシー運転手を育成・全国に送り出すプロジェクトを2025年夏から始動予定です。現地で日本語教育と運転技術を教え、日本での二種免許取得・研修を経て全国のタクシー会社に紹介する仕組みで、年間300人規模の受け入れを目指しています。
このように、地方の教習所が主導し、登録支援機関や現地政府と連携した「送り出し型モデル」が現実化しつつあり、地方における外国人ドライバー導入の可能性が着実に広がっています。
現在、ベトナム人は日本国内で最も多く在留している外国人労働層の一つであり、特定技能制度でも多くの実績があります。特にまじめで勤勉、地域社会への順応力が高いことから、都市部だけでなく地方でも活躍が期待されている人材層です。
実際に、介護や農業など他分野ではベトナム人が中山間地域に定着し始めており、今後はタクシー業界でもその動きが加速すると見られています。
| 課題 | 対応の方向性 |
|---|---|
| 地理・接客の習熟 | カーナビ活用と接遇研修の強化 |
| 地方での生活基盤 | 登録支援機関との連携による住宅・生活支援 |
| 地元住民との関係性 | コミュニティ参加の促進、多文化共生 |
→ 国・自治体・支援機関・企業が連携し、「安心して働ける環境づくり」を整えることで、特定技能ドライバーの地方定着は現実のものとなるでしょう。
-
🔹徳島県では、教習所・登録支援機関・現地政府が連携し、ベトナム人ドライバー育成の全国展開に乗り出している。
-
🔹登録支援機関と紹介制度の活用により、来日前から生活・免許・就業まで一貫した受け入れ体制が整備されつつある。
-
🔹地特定技能制度の活用によって、地方の交通インフラ維持と国際連携が両立する、新たな人材モデルが形になり始めている。
今後、徳島発のこのモデルが、地方の交通課題を解決するロールモデルとして全国に広がることが期待されます。
📍今回紹介した関連記事のご案内
▼登録支援機関を活用するメリットについてまとめた記事はこちら
👉特定技能外国人の採用方法と登録支援機関・紹介会社の正しい活用ポイント
関心のある方は併せてご覧ください。