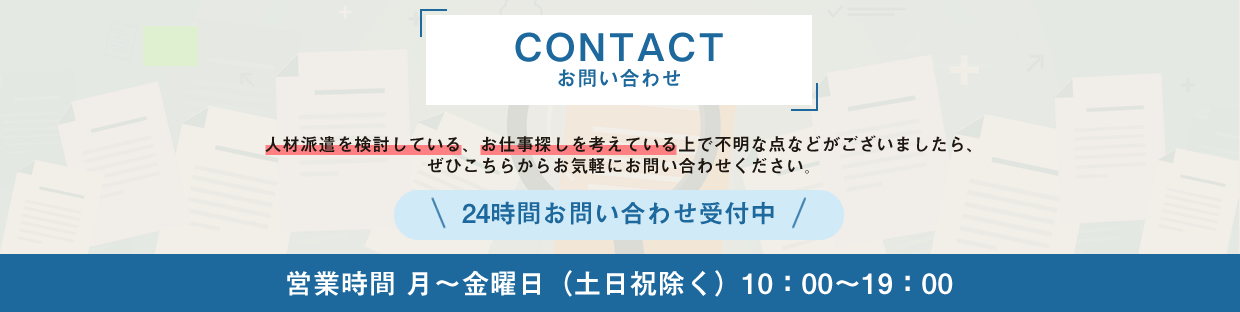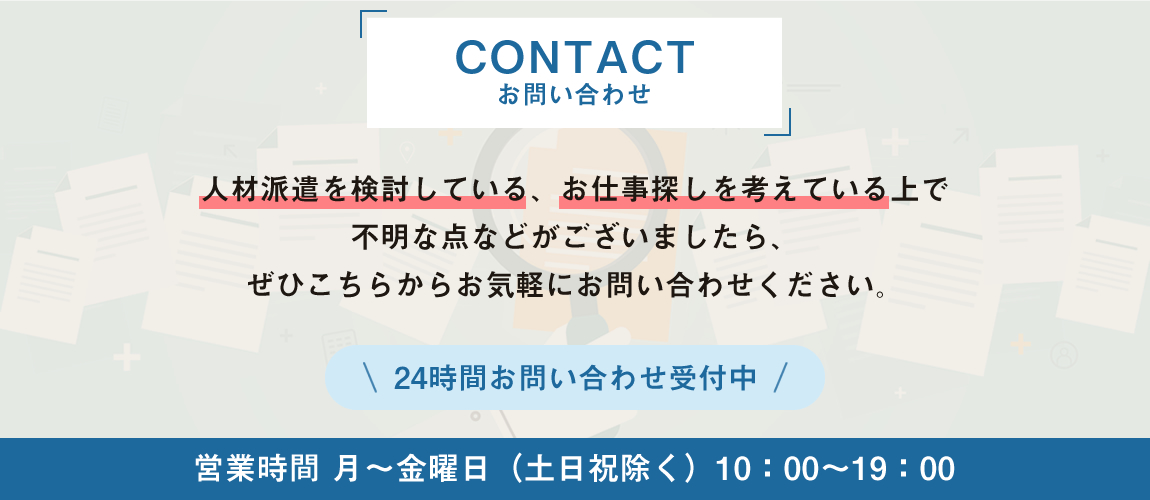特定技能制度を活用して「特定技能紹介」を行う企業や、「登録支援機関」を通じて外国人を雇用している事業者にとって、税務や年末調整の対応は欠かせない実務のひとつです。
特定技能外国人も日本人と同様に、所得税や住民税の納税義務がありますが、その手続きには文化や制度の違いに配慮した対応が求められます。
今回の記事では、特定技能外国人の税務対応に関して、雇用契約や登録支援機関が押さえておきたい実務ポイントをわかりやすく解説します。
特定技能外国人を雇用する場合、雇用主(請負事業者)は給与から所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収を行い、適切な控除申請を支援する必要があります。
特定技能外国人が日本で働く場合、給与から毎月の所得税を源泉徴収する必要があります。
これは日本人と同じ扱いで、企業(または請負元)が税金を給与からあらかじめ差し引き、納税を代行する仕組みです。
1年間に支払われた給与に対して、年末調整によって最終的な税額が精算されるのが一般的です。
ただし、年収が2,000万円を超える場合や、複数の事業所から給与を得ている場合には、別途確定申告が必要になります。
また、外国人が家族を日本国外に残している場合、扶養控除を申請する際には「親族関係書類」や「送金証明書」などの提出が求められます。
これらの書類は日本語訳の添付や、国によっては在外公館での認証が必要となるため、事前に準備を進めておくことが重要です。
-
🔹1月1日時点で日本に住所がある外国人は住民税の支払い対象
-
🔹税額は前年所得によって決まり、6月から翌5月まで12回で納付
-
🔹住民税の未納は在留資格の更新に影響する可能性あり
-
🔹転居や出国時の手続き(届出・一括納付)にも注意が必要
→ 雇用元の企業や「登録支援機関」は、住民税の対応についても外国人に分かりやすく案内することが求められます。
-
🔹日本に住所がなく、過去1年以上居所がない「非居住者」には課税対象外のケースあり
-
🔹特定技能1号は通常、居住者扱いとなるため対象外が多い
-
🔹出身国と日本の租税条約により、一定条件下で所得税・住民税が免除される場合もあります
-
例:ベトナム→原則通り、中国→教育訓練所得などに限定免除
→ 免除を受けるためには、給与支払者を経由して税務署や自治体へ適切な届出をする必要があり、「登録支援機関」を通じた案内が重要です。
| ステップ | 必要書類・対応 |
|---|---|
| 扶養控除申請 | 扶養親族の証明書(海外在住の場合は翻訳や領事認証) |
| 年末調整実施 | 雇用元企業が給与データを集約・源泉徴収を確定 |
| 給与所得が高額な場合 | 確定申告の案内と補助(母国語対応含む) |
-
🔹扶養控除の要件確認:海外扶養家族の書類は翻訳・認証が必要
-
🔹控除適用の誤り防止:扶養申請の有無や該当条件を書類で正確に把握
-
🔹在留資格更新との連携:納税状況は在留資格更新に影響するため、税務管理は必須
-
🔹言語サポート:母国語や英語で制度説明を提供し、誤解を防止
-
🔹特定技能外国人は、雇用契約先でも確実に税金納付義務がある
-
🔹「登録支援機関」や「特定技能紹介」の企業は、税務手続きのアナウンスと書類サポートが重要
-
🔹扶養控除や租税条約の活用には、適切な書類と手続きが不可欠
-
🔹税に関する誤解や遅延が在留資格の問題にもつながるため、実務は慎重に行う
特定技能外国人を支援する上では、税務面での正しい理解と、実際の対応力が企業の信頼にもつながります。 制度を正しく活用することで、外国人材の安定的な受け入れと、より良い労働環境づくりが可能になります。