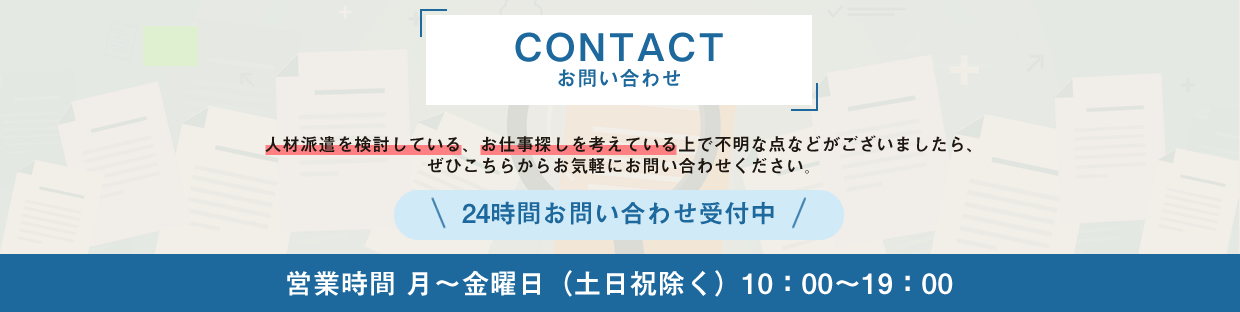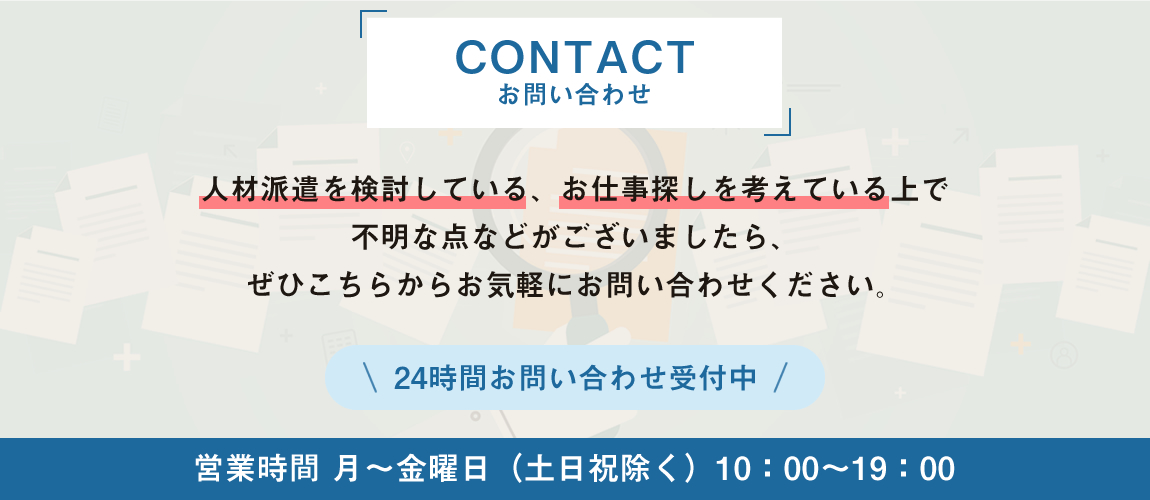外国人労働者の採用が増える中、企業の現場では文化や価値観の違いによるトラブルが少なくありません。請負企業や登録支援機関、特定技能制度を活用している企業にとっても、こうした課題は日常的です。
本記事では、外国人労働者が経験する差別の実態、その原因、そして解決策について解説します。また、特定技能人材の紹介や請負サービスを提供する登録支援機関の役割についても触れていきます。
外国人材と一緒に働く現場では、国籍や宗教、働く価値観の違いが原因で、意思疎通のすれ違いや職場ルールの認識ミスが起こることがあります。特に、請負現場や短期的に就労する特定技能人材が多い現場では、初期段階でのフォローが重要です。
-
🔹報連相が伝わらない:報告・連絡・相談の文化は日本独自のもの。曖昧な指示が誤解を招くことも。
-
🔹時間感覚の違い:時間厳守が当然とされる日本に対し、他国では柔軟な時間感覚を持つ場合も。
-
🔹上下関係や指示の受け止め方:国によっては、上司との距離感が非常に近い、または非常に遠いといった文化差がある。
-
🔹宗教や習慣の違い:勤務時間中の祈りや食事制限など、配慮が求められるケースもある。
-
文化の違いを前提とした採用設計
-
採用時に文化や価値観の違いを事前に説明し、互いの理解を深める。
-
-
やさしい日本語や翻訳ツールの活用/span>
-
指示は短く具体的に、誤解を避ける工夫を。
-
-
マニュアル整備と多言語対応
-
作業手順や就業ルールを多言語で提供。
-
-
教育とOJTのバランス
-
特定技能人材には制度上、支援・教育の義務もあるため、現場と連携したOJTを。
-
-
マネジメントとメンタルサポート
-
日常的な対話を通じた信頼構築が、長期就労につながる。
-
たとえば、大阪エリアでは製造業や飲食業などで「特定技能1号」人材のニーズが高まっています。紹介会社を通じて採用する場合でも、文化教育や支援体制をどう整えるかが重要です。
また、請負契約の現場では、指揮命令系統や安全衛生面での教育責任が複雑化しやすいため、外国人労働者へのフォローアップが企業の信用にも直結します。
「登録支援機関」は、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、日本での生活・就労支援を行う存在です。
たとえば、
-
▹生活オリエンテーション
-
▹日本語学習の支援
-
▹相談対応や行政手続きの補助
など、現場では手が回らない部分のサポートを行うことで、企業と外国人の橋渡しをしてくれます。登録支援機関を探している企業は、実績や対応言語、現場対応力を確認して選びましょう。
外国人労働者との文化や価値観の違いは、適切に対処すれば強みにもなります。特定技能人材を紹介する企業や、請負契約を結ぶ企業にとっても、文化理解と支援体制の整備は、安定した労働環境づくりの鍵です。
登録支援機関と連携し、現場での支援を強化することで、トラブルを未然に防ぎ、定着率の向上にもつながります。
📌 関連記事のご案内
文化的な価値観や習慣の違いによる職場トラブルの背景には、差別や偏見といった社会的な課題も関係しています。 今回ご紹介した予防策とあわせて、差別問題についても理解を深めることで、より良い共生職場づくりに役立ちます。関心のある方は下記コラムもご覧ください。
👉 日本の就労市場で外国人労働者が直面する差別の実態と解決策